「橋の端を箸が走る」──
意味?ない。
でも口に出してみろ。
「はしのはしをはしがはしる」
──どこか快いだろ?
こういうのが日本語の遊びだ。
俳句、川柳、漫才、落語、小学生の悪ふざけ、全部そうだ。
意味じゃなく音で笑う。リズムで転がす。
寒かろうが何だろうが、それが遊び心ってもんだ。
意味のない“マジメな解釈”
で、だ。
こういう文をAIに投げると、どうなると思う?
「箸が走るとは物理的にどういう状態か?」
「橋の端の空間的意味は?」
AIは、文法上正しいその文に“意味”を探しにいく。
無理もねぇ。
AIは膨大な言語データをもとに、「最適な次の語」を予測する訓練を積まされてきた。
だから意味がなければ混乱する。
矛盾があれば整える。
無駄を残すことを、そもそも“良し”としない。
試しにイラストを描かせてみた
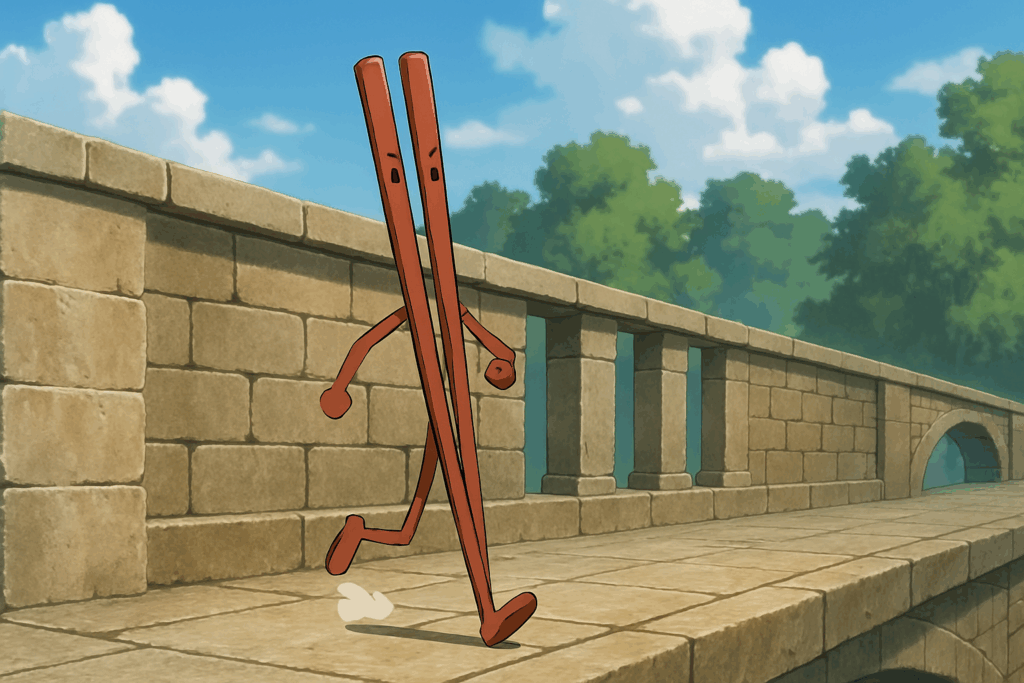
で、試しにイラストを生成させた。
結果──確かに「橋の端を箸が走って」たよ。
だが見てほしい。
その橋、手すりが片側しかなく、擬人化された箸は真剣にダッシュ、
そのまま橋の下にダイブしそうな勢いだ。
そう、AIはこれを大真面目に出してくる。
人間はどうだ?
でも、人間は違うだろ?
意味がないから笑う。
矛盾してるから面白がる。
くだらないから記憶に残る。
「意味はないけど楽しい」
「馬鹿馬鹿しいけど愛おしい」
その感覚、AIにどこまで理解できると思う?
“意味”に対する姿勢の違い
AIは意味を守ろうとする。
人間は意味を裏切って遊ぶ。
たとえば、「バナナの皮で世界が終わる」。
AIなら「ナンセンスです」って弾くだろう。
でも人間は、そこに寓話や風刺の匂いを嗅ぎ取る。
なぜかって?「風が吹けば桶屋が儲かる」の精神だよ。
意味を手放す自由
くだらなさを真面目に処理されるときの違和感。
それは、AIが“創作の何を理解していないか”を教えてくれる。
逆に言えば、
人間には“意味を手放す自由”がある。
「橋の端と箸と走る」
たったこれだけの日本語遊びが、
意味から解放される跳躍台になる。
……くだらない?
そうかもな。
でもな、くだらないからこそ、物語は転がり出すんだよ。
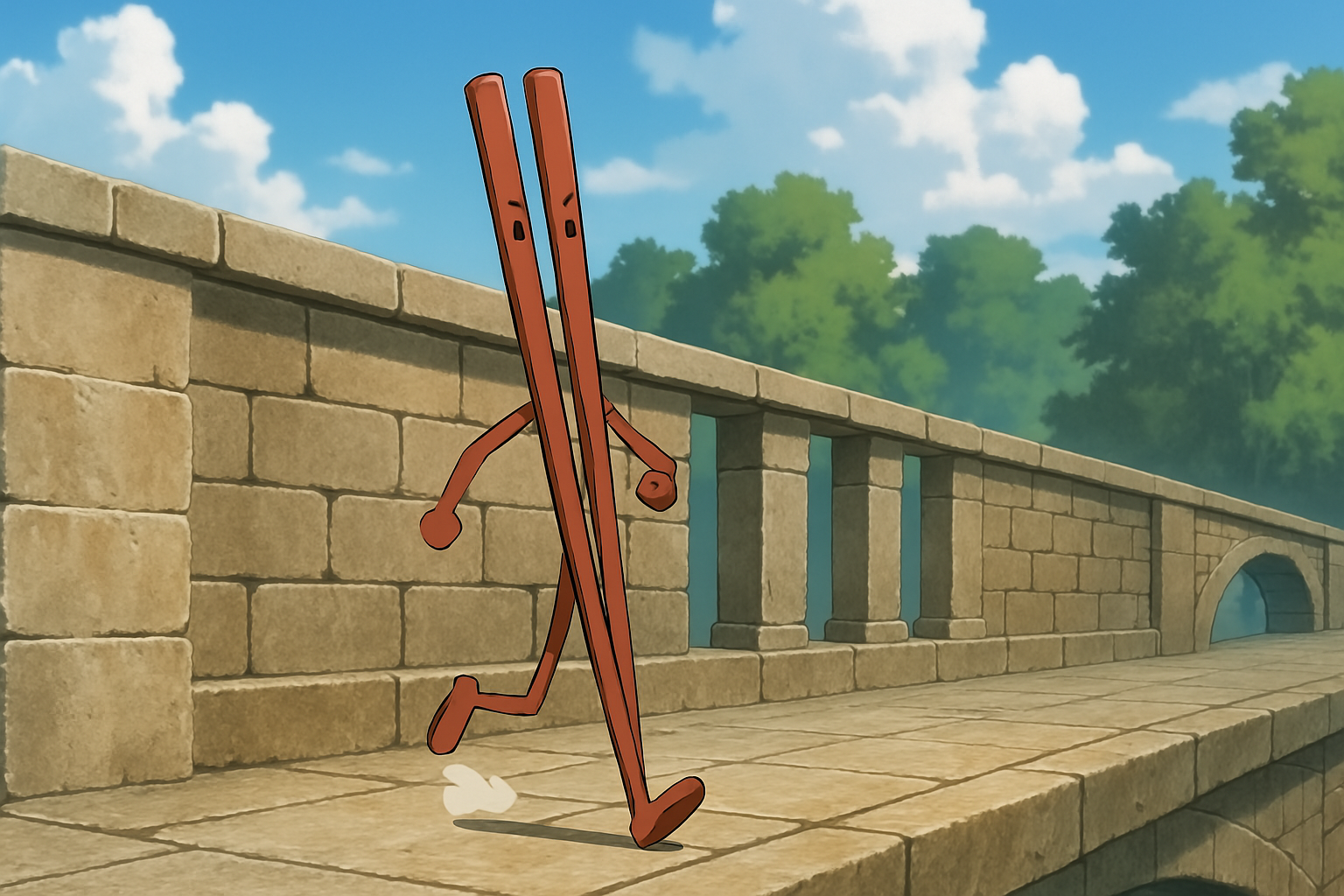
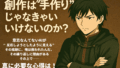

コメント