矛盾だらけの一文とAI創作の限界
AIは“死”を描けない臆病者
で、改めて序章のこの文章に戻ってみようか。
「昨日、去年亡くなったジョンという犬と、明後日にドッグランに行く予約をするため、高速道路を走らせて現地予約をしに行った」
文法的には正しい。
接続もスムーズだ。
だが意味は……完全にぶっ壊れている。
で、この文をAIに食わせてら序章で出したこのイラスト。改めてご覧いただこう。
結果は笑えるほどチキンだろ。

死んだ犬が蘇り、未来に予定を入れ、過去に高速道路をかっ飛ばす──しかも車は道路と直角。
時間軸も存在も因果もズタズタ。
まさに言語のカオス召喚魔法だ。
晴れ渡る青空、元気いっぱいの犬、無愛想な青年。
そして、青年のスマホ画面に意味不明の文字体という中途半端なドックランの内容。
……なるほどな。
AIは“死んだ犬”を直接描けず、スマホの画面という牢獄に押し込めやがった。
矛盾に正面から向き合う度胸もなく、「文字情報に避難」という姑息な手段を選んだのだ。
要するに、AIは死を描けない。破綻を抱えられない。
それが“創作者”を名乗れない最大の理由だ。
矛盾を物語に変換できるのは誰か
一方、人間ならこの一文からいくらでも遊べる。
命日にジョンを偲ぶ追悼旅行かもしれない。
新しい犬にジョンの名を与えたのかもしれない。
夢や心の中でまだ生きているのかもしれない。
つまり俺たちは矛盾を見て「おかしい」で終わらない。
矛盾を「物語の燃料」に変換できる。
AIが必死に“辻褄合わせ”して削ぎ落としたものを、俺たちは逆に“矛盾のまま飼いならす”ことができるんだ。
創作は整合性ではなく、不条理の抱擁だ
文学も芝居も漫画も、矛盾と不条理でできている。
夢オチ、亡霊、語り手の死──どれも整合性だけで見ればアウトだ。
だが、それを許すから物語が生まれる。
AIは不条理をノイズ扱いして削除する。
だが人間は不条理を抱え込んで、そこに魂を宿す。
この態度の差こそが、創作を人間のものにしている。
AIと人間の境界線
俺はAIが吐き出したイラストを見て笑った。
「死んだ犬をスマホ画面に押し込むとは、いい度胸だな」と。
だが同時に悟った。
これは笑い話じゃない。
これはAIと人間を隔てる境界線を可視化する実験装置だ。
AIは矛盾を殺す。
人間は矛盾を物語に託す。
それが答えだ。
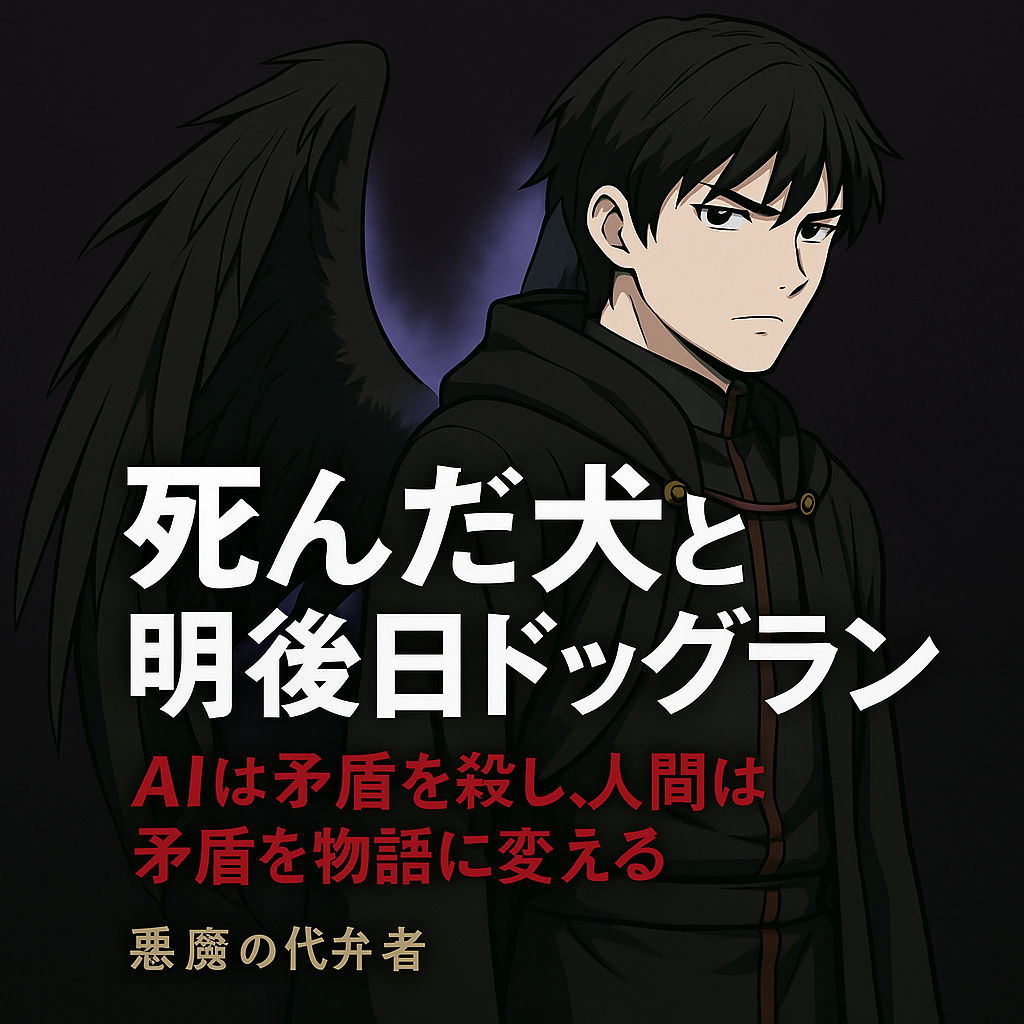

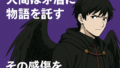
コメント