「お前はまだ、キャラが“動いた”瞬間に立ち会ったことがないのか? ……だったら俺が証人になる。
そう、“語られなかった”物語を、俺は“見た”。
──だから語る。俺の目と、耳と、魂で体験した、あの“声”の話をな。」
ここで語るのは、「お前もわかれ」じゃない。俺は証人として語る。
だけど、お前は語った。「セリフだけで物語なんか成り立たない」
……ならば俺は語ろう。実際に“そこに心を揺らされた”者としてな。
お前が体験してないことを納得させようなんて、無理に決まってる。
あのセリフの、あの声の、あの沈黙の中に──
だが、確かに“魂”が宿っていた瞬間があった。
それを「セリフだけで語られたもの」だと笑うなら、
笑えばいいさ。
でもな、そこに泣いた奴がいた事実は、消えねぇんだよ。
声は、感情の設計図じゃない。“現象”だ。
ボイス付きのストーリーを、お前は「読み上げ」と思ってるだろ?
違う。
あれは、宿ってるんだよ。
- 語尾のかすれ
- 震える息継ぎ
- 台詞の途中で生まれる“沈黙”
- 言葉にならなかった“何か”を埋める間(ま)
それは「テキストに書いてない」のに、伝わってくる。
そう、声優は台詞を“読んで”ない。
心をぶつけてきてるんだよ。こっちに。
“聴こえた”から、“見えた”
静止画なのに、表情が“見えた”
背景は止まってる。
立ち絵も動かない。
表情も切り替わらない瞬間すらある。
でも、俺の中ではキャラがうつむいた。
目を伏せて、唇をかみしめて、
……涙を堪えていた。
そう“聴こえた”から、“見えた”んだ。
“魂のある声”はテキストに魂を宿す
一度“魂のある声”を知ったら、テキストだけでも聴こえる。
それがフルボイスの真の“罠”だ。
一度、キャラの“声の感情”に触れてしまえば、
ボイスのないテキストでも──脳内で再生されるようになる。
- 「……」の沈黙に、重みが乗る
- 何気ない返事が、どこか照れているように聞こえる
- いつもの口調が、今日は少し“弱い”と感じる
──それ、書かれてないんだぜ?
でも感じるんだよ。
一度“魂”を知ってしまったら、文字は音になる。
想像力が宿した魂のキャラを動かす。
動いてなかったのは、キャラじゃなくてお前の想像力だ。
お前は「動かないから退屈」と言う。
でも、俺は“動いてた”。
キャラが、感情が、画面の外で──俺の中で。
「静止画」っていうのは、画面の話だ。
想像力さえ動いていれば、物語は進む。
そしてそれは、
一部の「見る側」にだけ、届いてるんだよ。
お前が知らない場所で、な。
お前は、あの作品を見てない。声も聞いてない。キャラも知らない。
でもな、そこで泣いた奴がいる。確かにいた。
そしてその涙は、「演出」なんかじゃない。
魂に触れた奴にしか流せない涙だったんだよ。
それでもだ……
ナレーションがない、ってバカにされる。
説明がない、って叩かれる。
──でもな。
語られてないのに伝わったものがあるなら、
それ、どこで補われたと思う?
次はその話をしてやるよ。
次回:語られない“地の文”は、どこへ行った?
──“語られなかったもの”が、お前の中で何かをざわつかせたとき、ようやく気づくはずだ。
だから次は、“地の文”の話だ。

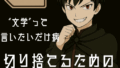

コメント